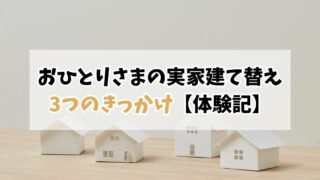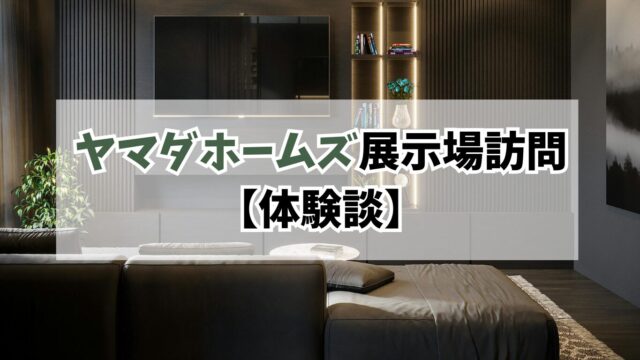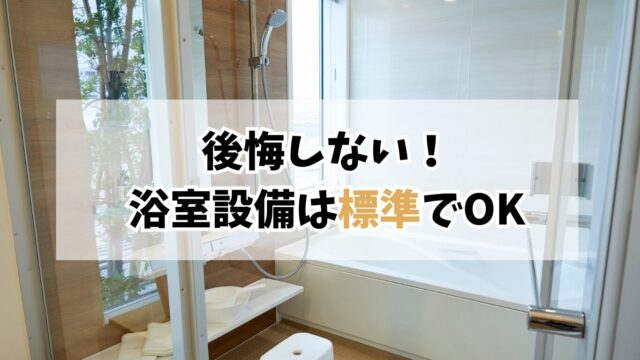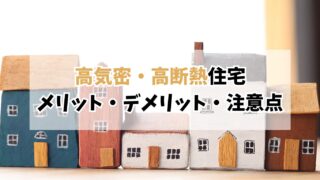40代おひとりさまの家づくり|実家建て替えで見直した3つの優先順位

40代おひとりさまの私は、実家の建て替えを決断しました。「一から家を建てるなら、暮らしそのものも設計しなおしたい」そう思ったのが出発点です。
この記事では、私が「広さや見た目のデザインより優先」した次の3つのこと
- 高気密・高断熱
- 将来を見据えた間取り
- 静けさと安心感
を、体験談を交えてお伝えします。
40代で家づくりを考え始めた方、実家を建て替えるか迷っている方のヒントになれば嬉しいです。
住み心地最優先!高気密・高断熱と”換気”のバランス
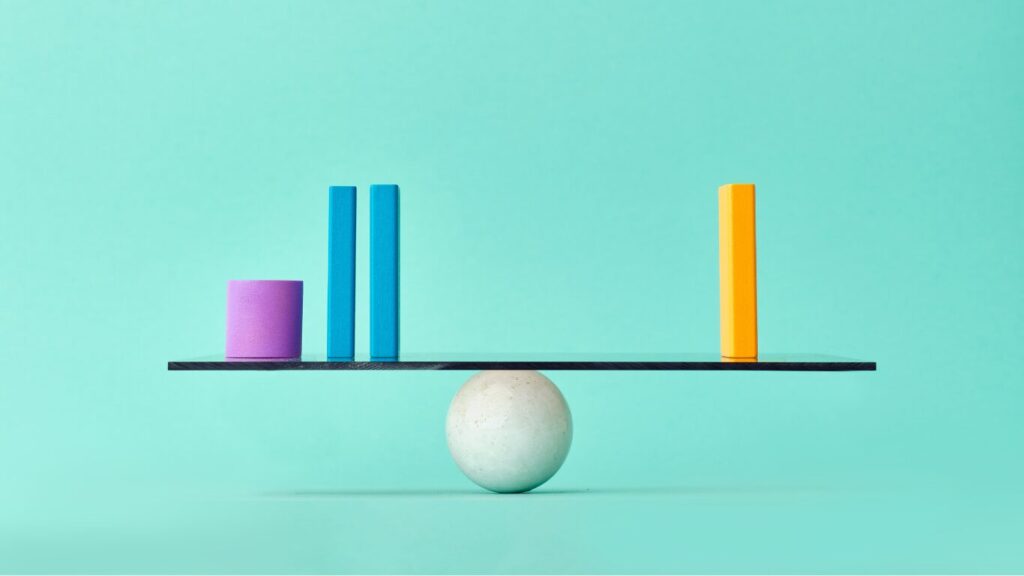
建て替え前の実家で感じた課題(暗さ・寒さ・湿気)
私の実家は、築40年以上の木造2階建て。正直、「快適な家」とは言えないお家でした。
- 1階は陽が入りにくく、常に電気を付けないと暗い…
- 陽が入らないので、カビっぽくなりやすい…
- 特にお風呂場や洗面所は、換気をしてもカビが生えてしまう状況…
- 冬は家全体が寒く、エアコンでは間に合わないので石油ストーブで部屋を暖める…
そこで、家を建て直すと決めたときにまず私が注目したのは、「冬も暖かく結露しにくい家=高気密・高断熱」でした。
気密性と断熱性が高い家だと、ヒートショック防止にも繋がるといいます。「家を建替えるなら、高気密・高断熱の家がいいな!」と考えるようになりました。
メリットだけじゃない。だから『換気』がカギ
ところが、高気密・高断熱にはメリットがある一方、実はデメリットもあるんです。
結露やカビが発生しやすい
換気不足による健康リスク
乾燥しやすい
高気密・高断熱の家は空調効率が上がり快適ですが、結露や乾燥するという課題もあります。結論として、『気密と断熱、換気のバランスが重要』ということを学びました。
気密・断熱・換気のバランスをどう取るか。それを良く考えなければ、家を建ててから後悔しかねません。
家づくりのパートナーとなる住宅メーカー訪問では、次を必ず確認するようにしました。
- 気密性能の実測有無:気密測定は全棟か/一部か
- 断熱性能の目安:例えば、その地域での基準との比較
- 換気方式:フィルターなどお手入れのしやすさも確認
- 結露対策:通気層や防湿施工の状況
- メンテナンス費:換気機器やフィルター交換の頻度など
見た目より家そのものの性能を先に固める。これが私にとっての家づくりの「土台」でした。
将来を見据えた間取りと動線:ユニバーサルデザイン+1階完結
同居する母と、未来の自分のために
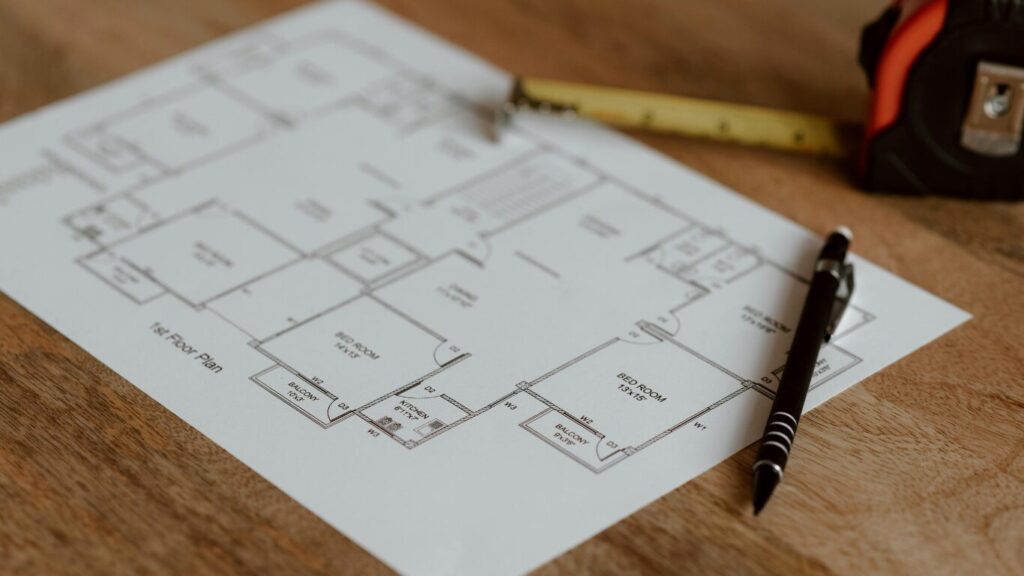 私は現在、70代の母と一緒に暮らしています。家を建て替えた後も母と暮らす前提で、ユニバーサルデザインを重視しました。
私は現在、70代の母と一緒に暮らしています。家を建て替えた後も母と暮らす前提で、ユニバーサルデザインを重視しました。
段差を減らす/引き戸中心/手すり想定など、「誰にとっても使いやすい」設計を軸にしました。
今から家を建てる場合は、そもそもユニバーサルデザインが基本になっているはずです。気になる方は、住宅展示場訪問などで、家の中の基本デザインがどのようになっているのか、しっかり確認しましょう!
狭小地×セットバックでも”暮らしやすさ”は作れる
私が家を建て直そうとしている場所は、いわゆる狭小地かつセットバックが必要な場所です。
確かに狭い土地ですが、今の母との暮らしや将来を見据えると、ちょうど良い大きさだと思います。日頃の生活動線を意識しつつ、LDKと水まわりを1階にまとめるなど、将来的に1階で生活が完結できるような間取り作りを心掛けました。
今はメインの寝室を2階に設置するけれど、将来的には1階に寝室を置く案も検討。設計士さんと納得がいくまで何度もラフプランを往復しました。
間取り作りは、「設計士さんへしっかりとこちらの希望をお伝えすること」が大切です。初めはなかなか慣れずに大変だとは思うのですが、大丈夫です。私でも回を重ねるごとにわかるようになりましたので、がんばりましょう!
打ち合わせで役立った質問例
設計士さんとの打ち合わせで確認しておきたい、主な内容をのせておきます。
- 収納計画:どのくらいスペースが確保できるか。
- 家事動線:例えば、玄関→パントリー→キッチン等の直線化ができるか。
- トイレ位置:音の配慮と夜間の動線ができているか。
- 将来の可変性:仕切りの追加や寝室を移動できる余地はあるか。
初めのうちは、設計士さんが考えるおすすめのパターンを聞いてみると良いですよ。
間取り作りに悩んだ際も、例えば「トイレの配置は、今の間取りだとどこがベストですか?」とか、「設計士さんだったら、ウォークインクローゼットはどこに設置しますか?」と聞いてみるのも手。プロ目線の”最短ルート”を教えてもらえます。
静けさと安心感:余白を生む収納計画と「モノの見直し」
物が多い家は、心もざわつく
 築40年以上の実家は、当時4人暮らし。そして…「家には、めっちゃ沢山モノがある!」
築40年以上の実家は、当時4人暮らし。そして…「家には、めっちゃ沢山モノがある!」
特に戸建ての場合は賃貸マンションなどと比べるとスペースもあるので、モノが溜まりやすいですよね…。引っ越し回数が少ないほど、モノは溜まりがち。見えない場所に”隠せる家”は、実は片づかない家でもあります。
モノが溢れると、部屋が狭くなり見た目もよろしくない。掃除も大変。物理的な空間が狭くなるだけでなく、気持ちも圧迫される気がします。これは、良くない!
というわけで、私が家づくりで目指したのは、静けさが感じられる余白。そのために、今からモノを減らすと決めました。
今からできる見直しチェックリスト
モノを減らして、スペースを確保する。余白が生まれることで、気持ちにも余裕が出てきませんか?心が落ち着くような暮らしをイメージしながら、家づくりも考えたいですね。
毎日触る物→定位置を決める(鍵・財布・常用薬)
洋服→1年着ていなければリサイクルショップへ
思い出の品→写真化する/ボックスに入れて保管(ただし、箱数は決めて今後増やさない)
収納設計→入れる物の量を先に決めて収納量を設計する
音対策→寝室の配置や窓の仕様(防音・複層)も同時に検討する
モノが多過ぎない生活を送ることで、心の静けさ・ゆとり、そして安心感が増す時間を過ごしていきたいなと考えています。
まとめ:優先順を言語化すると、家づくりはブレない
今回は、私が家づくりで大切にしたかった3つのことをご紹介しました。
- 性能と換気のバランス(高気密・高断熱+換気)
- 将来を見据えた間取りとユニバーサルデザイン
- 静けさと安心感をつくる余白(収納と持ち物の見直し)
家を建てるのはあなた自身!施主はあなただからこそ、自分の優先順位を先に言語化しておくと、打ち合わせでの判断も速く、後悔が減ります。
家づくりで譲れないポイントは、人それぞれ。ご自身なりの「家づくりにおける優先順位」を、ぜひじっくり考えてみてくださいね。楽しみながら、家づくりを進めましょう!
この記事を読んだ方におすすめ:
おひとりさまの実家建替え体験記|家づくりのきっかけになった3つの出来事