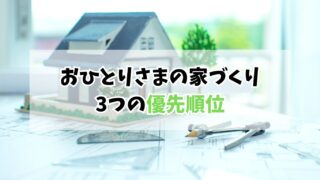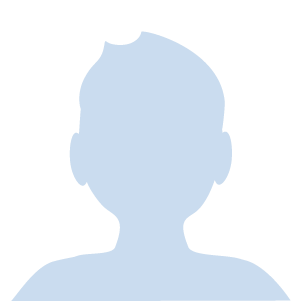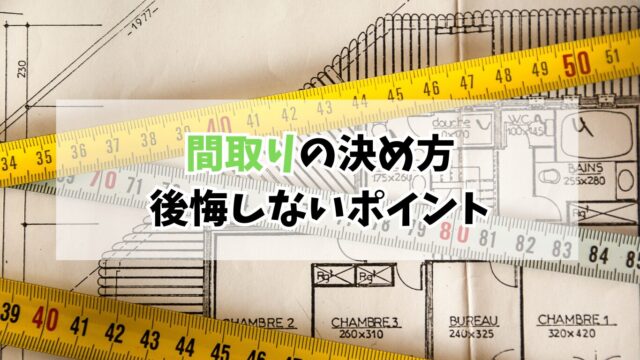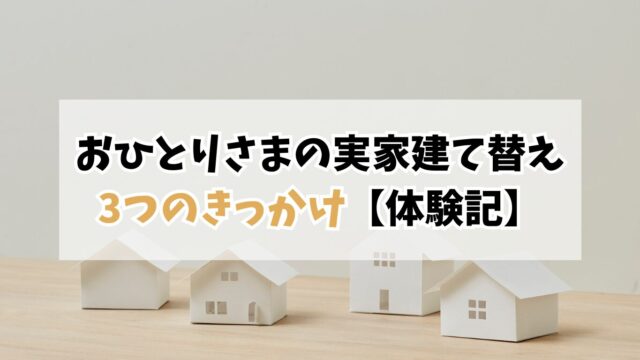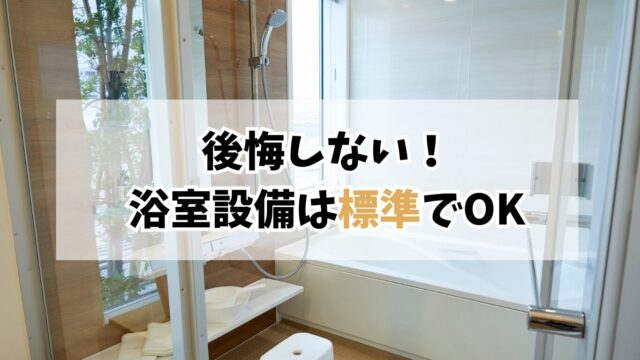地鎮祭とは?流れ・費用・やって良かった実体験まとめ
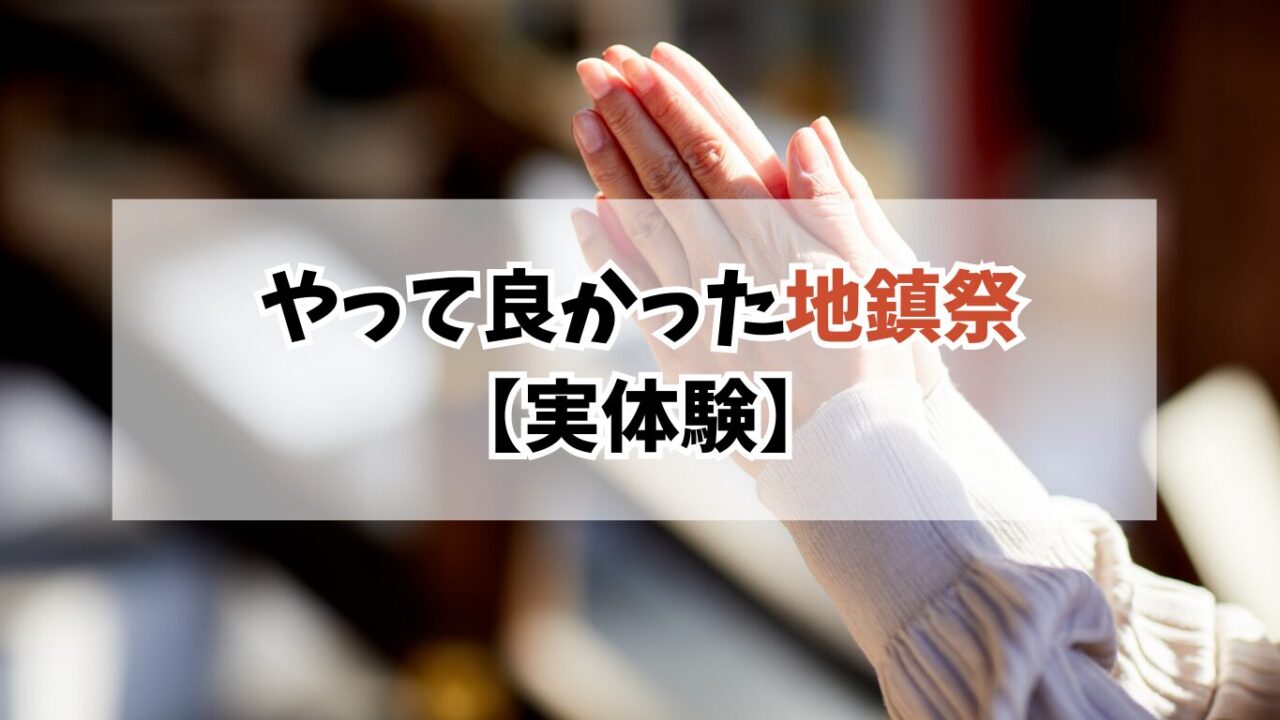
家づくりの始まりには、少し特別な儀式があるのをご存じですか?
それが「地鎮祭」です。
2025年5月、私もついに地鎮祭を行いました!
この記事では、
- 地鎮祭ってどんな意味があるの?
- 実際の流れは?
- 当日の服装や準備ってどうすればいい?
そんな疑問に、体験談を交えながらお答えします。
これから家づくりを始める方、地鎮祭をやるかどうか悩んでいる方にとって、この記事が参考になれば嬉しいです。
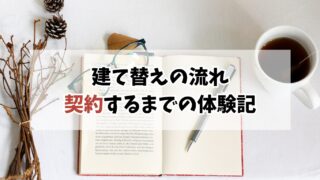
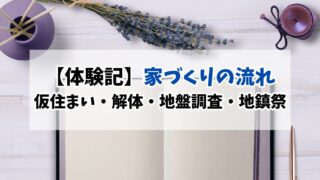
地鎮祭とは?意味と目的を簡単に解説
 地鎮祭(じちんさい)とは、建築工事を始める前に土地の神様へ工事の安全を祈願する儀式のこと。
地鎮祭(じちんさい)とは、建築工事を始める前に土地の神様へ工事の安全を祈願する儀式のこと。
「これからこの土地にお世話になります」と神様にご挨拶し、工事中の安全・家族の繁栄を願うものです。
実際に地鎮祭を行うときは、次のようなメンバーが参加します。
- 施主(建主)=家を建てる人
- 施工会社(工務店など)の担当者
- 神社の神主さん
神社に依頼をすれば、祭壇の設営や供物などはすべて準備してくださいますよ。
施主が用意するのは、主に次の2つだけ。
- 御初穂料(おはつほりょう):神主さんへの謝礼(一般的には3〜5万円)
- 奉献酒:神前にお供えするお酒(地元の酒屋で購入可)
つまり、特別な知識がなくても大丈夫!神社の方が、すべてサポートしてくれます。
私も正直、最初は「やった方がいいの?やらなくてもいいの?」と迷いました。
でも結果的に、家づくりのスタートを神様に見守ってもらう時間は、とても意味のあるものでした。
地鎮祭当日の様子|服装や天気、準備のリアル体験談
 では、いよいよ当日の話。
では、いよいよ当日の話。
地鎮祭には、私・母・弟の3人で参加しました。
天気はあいにくの雨…。でも、これがまた記憶に残る一日になったんです。
祭壇はすでにテントの下にしっかり設営されていて、榊や果物、野菜などがずらり。神主さんが、静かに準備を整えていました。
地鎮祭の服装ポイント
服装は、「派手すぎず、地味すぎず」を意識。私は、黒のワンピースに控えめなアクセサリー。母も黒系でまとめていました。弟は紺色のシャツ+チノパン。
スーツまでは不要ですが、“きちんと感”のある服装がおすすめです。
- 黒・紺・グレーなど落ち着いた色味を選ぶ
- 派手な柄や露出は避ける
- 靴は泥がついても大丈夫なローヒールやスニーカー
- 雨の日は長靴でもOK!
私たちはとても緊張していたのですが、神主さんはとても穏やか。雨の中でも、「今日は良い日になりますよ」と、にこやかだったのがとても印象に残っています。
その一言のおかげで、緊張もほどけました。
雨の日の地鎮祭は大変でしたが、あとから振り返ると不思議と心に残る体験になりました。
家づくりの過程には、このような「予定外の出来事」が結構あります。
【建築確認トラブル実録】地鎮祭後に工事が進まない!? 2025年法改正の影響とは
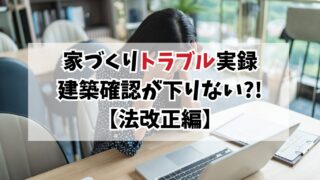
地鎮祭の流れを解説|姐さん家の場合
地鎮祭の流れは神社によって多少異なりますが、私が参列した地鎮祭の儀式は以下のような順序で進行しました。
- 修祓(しゅばつ):神主さんが参列者・土地をお祓い
- 降神(こうしん)の儀:土地の神様を祭壇にお迎えする儀式
- 祝詞奏上(のりとそうじょう):神様へ工事の安全と家族の繁栄を祈願
- 四方祓の儀(しほうばらえのぎ):土地の四隅と祭壇前の盛砂を清める
- 地鎮の儀(じちんのぎ):施主・施工者が「えいっ!」と掛け声をかけながら砂山に鍬を入れる儀式。いわゆる鍬入れ(くわいれ)
- 玉串拝礼(たまぐしはいれい):玉串を供えて二礼二拍手一礼
- 昇神の儀(しょうじんのぎ):お招きした神様をお送りする儀式
- 神酒拝戴(しんしゅはいたい):お供えしたお神酒を戴き儀式終了
特に印象に残っているのは、⑤の「地鎮の儀」です。
私、ここで初めて人前で「えいっ!」って叫びました(笑)
この「鍬入れ」こそが、家づくりの始まりを象徴する大切な瞬間なんです。
神主さんがその都度「次はこちらへ」「では施主の方どうぞ」と案内してくれるので、初めてでも安心です。
途中、施工会社の方が写真を撮ってくれていて、後日データを送ってくれたのも嬉しかったポイント。
実際にやってみて感じたこと|心が整う「特別な時間」
正直、地鎮祭の最中も少し緊張していました。
神主さんの祝詞が響く中、雨音がテントを打つリズムも加わると、その場の空気がスッと引き締まって。神聖な場所になっていくのを感じたんです。
そして、印象的だったのが「地鎮の儀」。
鍬を入れるとき、神主さんの合図で「えいっ!」と声を出すんですが、これがちょっと照れる…(笑)。でも、不思議とその一声で「気合い」が入るんですよね。
私が緊張している横で、工務店の担当さんが先にお手本を見せてくれて、「なるほど、あんな感じね」と構えていたら、次に神主さんが指名したのはまさかの――弟!
私:「えっ、弟なの!?」
弟:「えっ??……え、えいっ!(照)」
これには弟も驚いていましたね。まさか、施主の私以外でも「えいっ!」の出番が回ってくるとは(笑)。まさかの展開に、思わず私と母は含み笑い。弟は苦笑い。
厳かな儀式の中にも、こうした「家族の思い出」ができるのが地鎮祭の良いところですね。
儀式が終わる頃には、「いよいよ、ここに私たちの家が建つんだ…!」と実感が込み上げてきました。
雨に濡れながらも、心の中はなんだか晴れやか。
神主さんの「これからの工事も安全に進みますように」という言葉が、胸にじんと残りました。
儀式が終わると、神主さんと一緒に全員で笑顔の記念撮影。雨は降り続いていましたが、とても清々しい気持ちになりました。
地鎮祭でもらったお供え物と御札
 地鎮祭が終わると、神主さんから
地鎮祭が終わると、神主さんから
- 祭壇に供えた果物や野菜
- 四神祓塩(しじんはらいしお)
- 御祈祷の御札(おふだ)
をいただきました。
お供え物は家に持ち帰って、家族で煮物やお味噌汁にしました。食べながら「今日は、いい日だったね」と話した時間まで、まるごと地鎮祭の思い出です♪
そして「四神祓塩」は、家の四方(東西南北)に置いて土地を清めるための御塩。
神主さんからは、「家が完成したら、このお塩を敷地の四隅に撒いてくださいね」と教えていただきました。
こうして一つひとつの儀式に意味があると知ると、「形だけの行事」ではなく、家を守る祈りの儀式なんだと改めて感じました。


地鎮祭をやるか迷っている方へ|姐さんの本音アドバイス
「地鎮祭って、絶対やらないとダメ?」――そう思っている方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、地鎮祭は「必須ではない。”けれど“やってよかった」行事です。
確かに、
- 費用(3〜5万円程度)がかかる
- 日程調整や準備が必要
- 最近は省略する家庭も多い
そんな理由で迷う方も多いと思います。
でも、私はこう思います。 「地鎮祭は、土地と家族を“つなぐ儀式”」なんだ、と。
これから建てる土地とちゃんと向かい合って、神様に手を合わせ、「ここに家を建てさせていただきます」と頭を下げる――この時間があることで、気持ちのスイッチが「家を建てるモード」に切り替わるんです。
母も弟も、終わったあとに「やって良かったね」と口をそろえていました。
もし今、「やろうか、どうしようか」と迷っている方がいたら――私は、迷ってるならぜひやってほしい!と背中を押したいです。
儀式としての意味以上に、「ここから始まるんだ」という気持ちを整える時間だったのかもしれません。
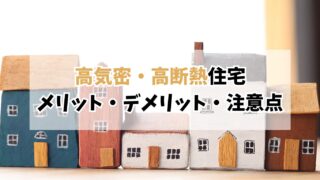
まとめ:やって良かった、地鎮祭!家づくりの原点に立つ日
 地鎮祭は単なる儀式ではなく、「家づくりのスタートラインに立つための時間」でした。
地鎮祭は単なる儀式ではなく、「家づくりのスタートラインに立つための時間」でした。
雨の中でも、緊張していても、その一つひとつが「自分の家を建てる」という実感につながります。
そして何より、家族で同じ時間を共有し、土地の神様に感謝を伝えることができました。
この経験は、家が完成してもずっと心に残り続けると思います。
まとめると、
- 地鎮祭は家づくりのスタートにぴったり
- 家族の絆が深まる貴重な行事
- やってみると、気持ちが整い前向きになる
これから工事が進むたびに、あの日の「えいっ!」の声を思い出しながら(笑)、完成の日を楽しみに待ちたいです。
私の家づくりの状況はこちら:
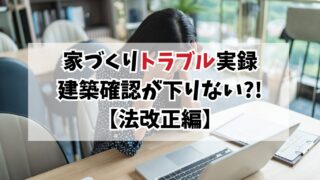

これから家づくりを始める方は、 【家づくりカテゴリ一覧】から私のリアルな家づくり記録と体験記事を読むのもおすすめです。
この記事を読んだ方におすすめ:
家づくり初心者が知っておきたいお金の話|費用・見積もり・予算のポイント解説
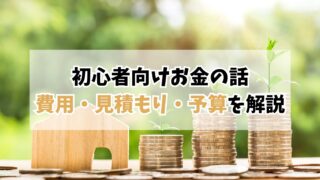
40代おひとりさまの家づくり|実家建て替えで見直した3つの優先順位